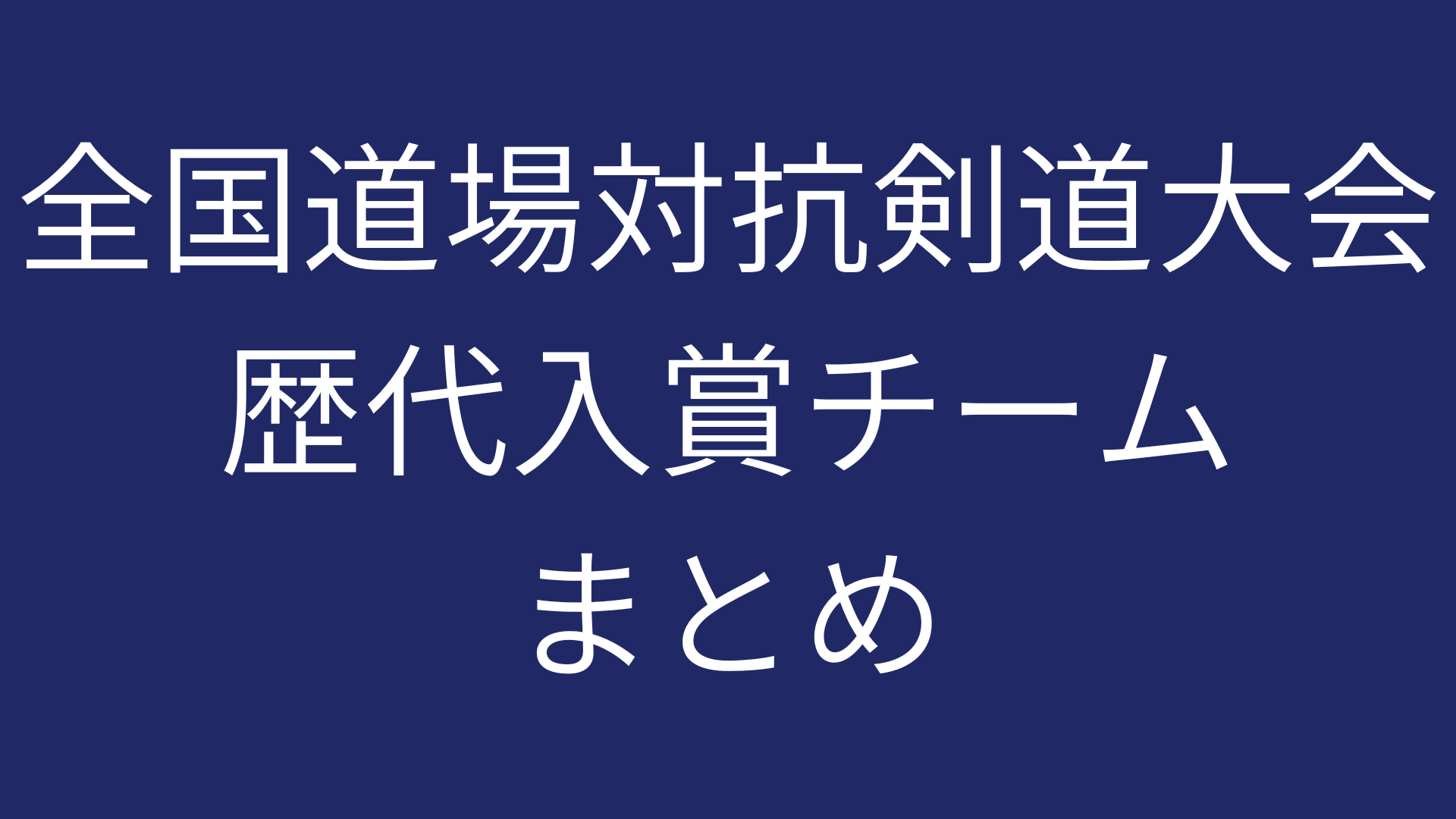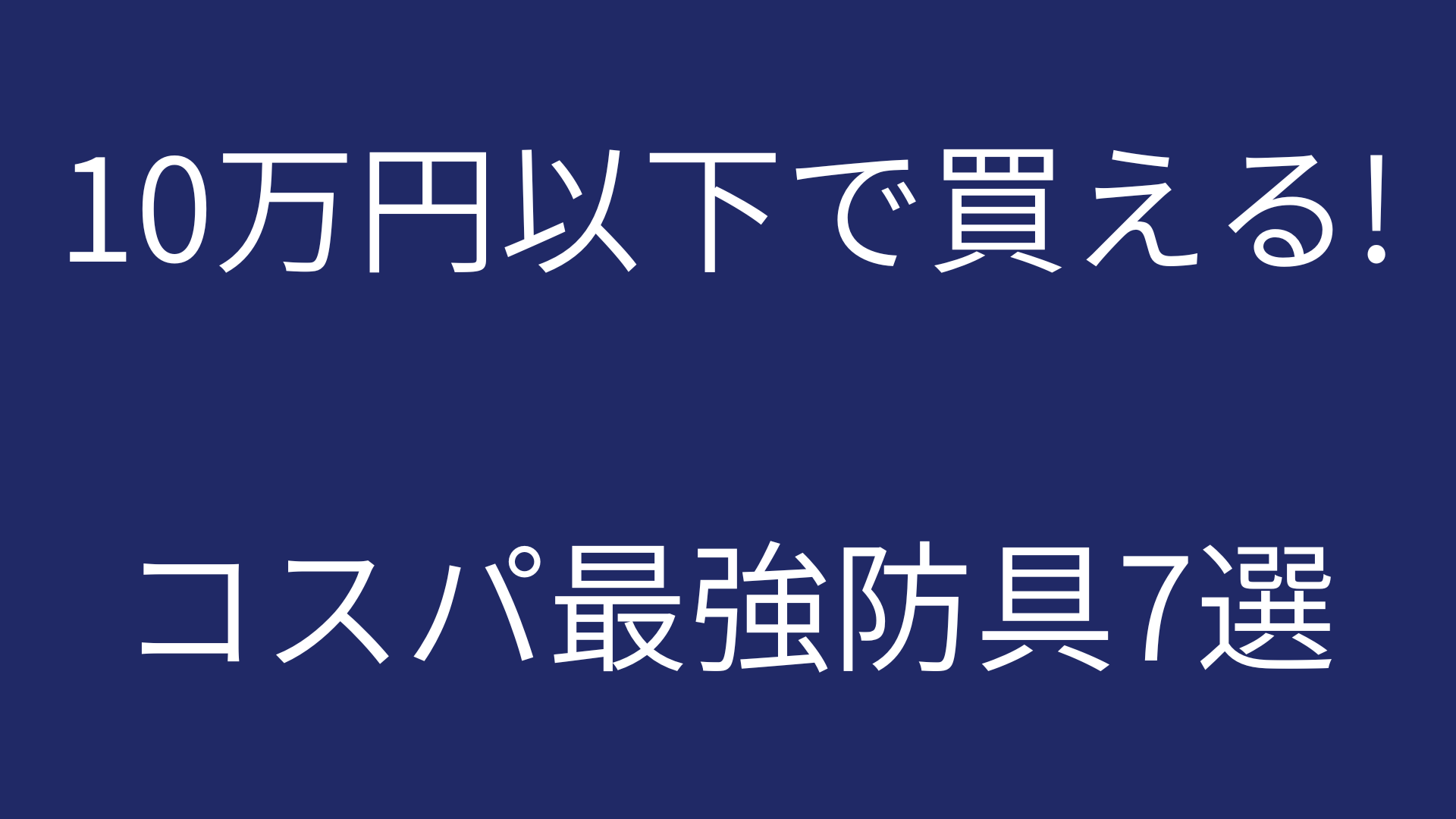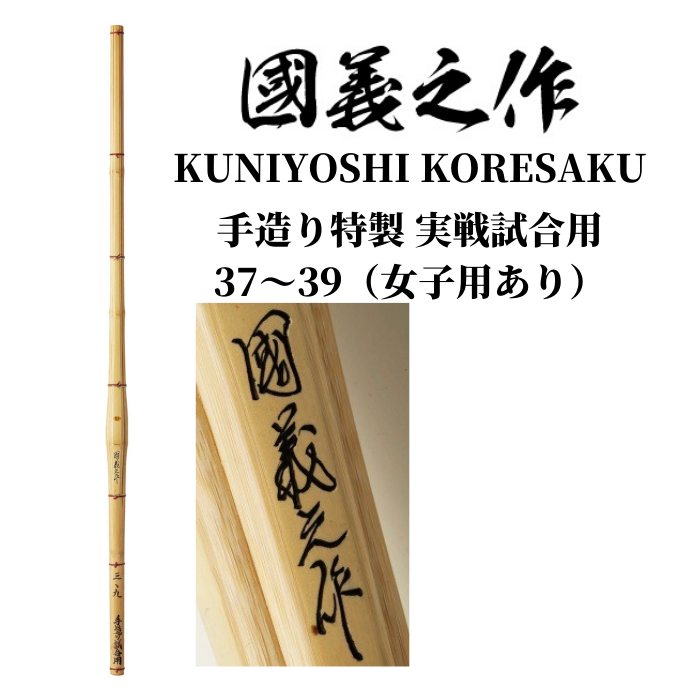As kendo equipment is subjected to various strikes during practice, it gradually becomes damaged and worn down.
Of course, if you take it to an armor shop for repairs, they will repair it nicely, but is it possible to do it yourself?
This time, we have summarized how to repair the rim and dodai yourself.
table of contents
How to paint the edges yourself
How to repair the dome yourself
In the case of Yamato body (resin body)
How to paint the edges yourself
<Materials and tools>
We recommend that you wear clothes that you don't mind getting dirty.
Although vinyl gloves do prevent cashews from getting on your hands, they make it difficult to perform delicate tasks such as painting the inside of the gloves, and cashews that get on the gloves may get on the surrounding area, so it is better to work with bare hands.
cashew
Cashews tend to harden easily, so do one step at a time.
If it gets on your hands, it won't come off even if you wash it with water, and if you then touch the mengane or futon with your hands, you may get cashews on the surrounding area. Try to be careful not to get it on your hands as much as possible.
If it gets on your hands, you can remove it by wiping it off with tissue paper or similar. However, this may irritate your hands.

brush
It is convenient to have a long one and one with the handle folded down to make it shorter.
*After using the brush, be sure to wash it with diluted solution, otherwise it will become hard and you will not be able to use it again.

Thinner
It is used to thin the cashew when it hardens, or to wipe it off when it adheres to the metalwork.

<Process>
1. Condition before work
The edges are peeling and the color underneath is visible.

2. Peel off
Peel off as much of the material as you can from any areas that are already starting to peel off.
It is recommended to use a stiff-bristled scrubbing brush, a metal brush, disposable chopsticks, or a flathead screwdriver.
You can also remove it using thinner, but this is not recommended as the thinner may soak into the inner fabric.
3. Paint only red and let it dry completely

When painting the red on the inside, be careful not to get it on the surrounding area (inner ring or bedding).
For a particularly beautiful finish, you can paint the innermost part of the ring by pressing it down with your fingers as shown in the photo above, taking care not to get the red on the inner ring fabric.
This is difficult to do with a long brush, so it is best to use a short brush or a long brush with the handle broken off.
When painting the outside, be careful not to let the paint spill over into the black parts.
If you get cashew stains on the center of the mengane, you can remove them with thinner. If you get cashew stains on the mengane right at the edge of the mengane, they will often have red stains, so you don't need to worry about it.
~After painting red~

4. Paint black

Be careful not to spill over into the areas already painted red. If you apply it thinly, it will create unevenness and look bad, so it's better to apply two or three coats for a more beautiful finish. (It's best to apply the second or third coat after it has dried to the point where it no longer sticks to your hands.)
After painting black

5. Let it dry completely
"Can I paint it with a marker?"
Some people may think, "Cashew marker is difficult to paint, isn't it? Can't I just paint it with something simple like a marker?" However, marker does not produce the same shine as cashew marker, and the finished product will be more purple than black.
Also, if you strike a surface painted with marker, the color of the marker may transfer to the bamboo sword and turn it black, so it is not recommended.
(Bonus) Re-dyeing your futon
Since you have already taken the trouble of repainting the edges, if the color of the futon has faded or if it has been exposed to salt, you can re-dye the edges of the futon, which will definitely make it look better.

<Materials and tools>
Indigo powder

Some are sold in liquid form, but some armor shops sell powdered form by the gram.
For the powder above, dilute the amount shown in the photo with 500ml of water before use.
~Diluted state~

Apply this diluted liquid evenly using a brush.
Allow to dry thoroughly.
~ State after painting ~

How to repair the dome yourself
There are three types of dodai: bamboo do, Yamato do (resin do), and fiber do.
Please note that the appropriate method varies depending on the individual.
There is also a limit to the damage that can be repaired.
If the wound is too deep and has reached the inside of the armor, there is nothing you can do about it yourself, so it is best to consult an armor shop.
In the case of a bamboo body
The surface is coated with lacquer.
Lacquer is hard, but scratches can be removed by polishing it.
Lacquer is usually applied thickly, so unless you polish it very hard, you won't remove all of it.
<How to remove scratches by polishing>
Material: Compound

This is an abrasive used to remove scratches on car bodies, etc. It does not fill in existing scratches, but rather polishes the surface to smooth out the area around the scratch and make it less noticeable.
<Process>
Scratched bamboo body (polish the red circled area)

Apply a small amount of compound to the scratch and rub it in a circular motion.

The body after polishing (the circled part was polished.)

The whitish scars are no longer noticeable.
<How to make scratches less noticeable by adding oil to give a glossy finish>
Materials: Protective oil for kendo equipment


This wax is made for the torso and chest.
It can also be used as bamboo sword oil.
Apply a generous amount and leave for about 30 minutes before polishing with a clean cloth.
It provides two benefits: gloss and surface moisturizing.
<Process>
Damaged bamboo trunk

Take Guardian Full Coat K with your finger and apply a thin layer all over.
Leave it for about 30 minutes, then wipe it off with a soft cloth.
Body after polishing

It became shiny and glossy, and scratches were no longer noticeable.
Yamato body (resin body)
The Yamato body is made of resin and is finished with paint applied to it.
Unlike lacquer, this paint is soft, so even if you try to make scratches less noticeable by scraping it with compound like you did with the bamboo body, the whole thing will end up with a whitish finish. Therefore, we do not recommend using compound. It is better to use an oil like Guardian Full Coat K mentioned above to make it shiny and make scratches less noticeable.
<How to make scratches less noticeable by adding oil to give a glossy finish>
Damaged Yamato Torso

Apply Guardian Full Coat K and polish.
Left half polished

It doesn't actually erase the scratches, but the gloss makes them less noticeable.
A scratch this deep can reveal the resin inside, so it cannot be repaired.
<How to remove scratches by polishing> *Not recommended
The right half of the Yamato body (the side that has not yet been polished)

Apply compound and polish.

The body after polishing.

The scratches are no longer noticeable, but it still looks somewhat whitish. In the case of the Yamato body, it is better to give it a glossy finish with oil.
In the case of a fiber body
In the case of fiber drums, just like bamboo drums, the paint applied to the surface is hard, so scratches can be removed by polishing with compound. However, as is the case with bamboo drums, scratches that are thicker than the paint cannot be removed with compound.
<How to remove scratches by polishing>
Damaged fiber trunk

Apply compound and polish.

The body after polishing. (The part circled in red was polished.)

It became so shiny that the photographer was visible in the photo.
<How to make scratches less noticeable by adding oil to give a glossy finish>
The damaged fiber body

Take a small amount of Guardian Full Coat K and polish.
~The body after polishing~

It's shiny and scratches are no longer noticeable.
summary
I thought it would be difficult to paint the edges and repair the body, but when I actually tried it myself, it wasn't that difficult, and it was actually a fun job! (As for the edges, painting the inside is certainly a difficult part.)
I felt that the power of specialized products was amazing when it came to the dodai. Using Guardian Full Coat K is just to give it a glossy shine with oil, and even if it loses its luster, you can always do it again in the same way to quickly restore it, so it's a simple job that anyone can do.
Kendo equipment should be carefully maintained and used for a long time.







 Armor Set
Armor Set
 面
面
 Kote
Kote
 胴
胴
 垂
垂
 Dogi
Dogi
 袴
袴
 bamboo sword
bamboo sword
 wooden sword
wooden sword
 armor bag
armor bag
 Bamboo sword bag
Bamboo sword bag
 Small items
Small items
 gift
gift
 Books/DVDs
Books/DVDs
 cleaning
cleaning
 Armor repair
Armor repair
 Kendo mask
Kendo mask
 Iaido
Iaido
 Japanese swords and art swords
Japanese swords and art swords
 Mitsuboshi
Mitsuboshi
 Tozando
Tozando
 Matsukan
Matsukan
 Japan Kendo Equipment Factory
Japan Kendo Equipment Factory
 West Japan Martial Arts Equipment
West Japan Martial Arts Equipment
 Glory Martial Arts Equipment
Glory Martial Arts Equipment
 Nobutake
Nobutake
 Busougi
Busougi
 Hakataya
Hakataya
 Shokodo
Shokodo
 Flag Ito
Flag Ito


 Value Set
Value Set
 Armor Set
Armor Set
 面
面
 Kote
Kote
 胴
胴
 垂
垂
 Dogi
Dogi
 袴
袴
 bamboo sword
bamboo sword
 wooden sword
wooden sword
 armor bag
armor bag
 Bamboo sword bag
Bamboo sword bag
 Small items
Small items
 gift
gift
 Books/DVDs
Books/DVDs
 cleaning
cleaning
 Armor repair
Armor repair
 Kendo mask
Kendo mask
 Outlet
Outlet
 Iaido
Iaido
 Japanese swords and art swords
Japanese swords and art swords
 Mitsuboshi
Mitsuboshi
 Tozando
Tozando
 Matsukan
Matsukan
 Japan Kendo Equipment Factory
Japan Kendo Equipment Factory
 West Japan Martial Arts Equipment
West Japan Martial Arts Equipment
 Glory Martial Arts Equipment
Glory Martial Arts Equipment
 Nobutake
Nobutake
 Taiyo Industry
Taiyo Industry
 Busougi
Busougi
 Hakataya
Hakataya
 Shokodo
Shokodo
 Flag Ito
Flag Ito
 Interviews Useful Articles
Interviews Useful Articles
 Size Measurement Guide
Size Measurement Guide
 GLOBAL SHIPPING GUIDANCE
GLOBAL SHIPPING GUIDANCE